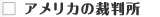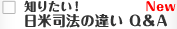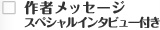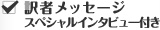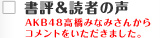岩崎書店編集部より
本書の翻訳者は、「黒魔女さんが通る!!」シリーズ(講談社)や「マジカル少女レイナ」シリーズ(岩崎書店)で大人気の石崎洋司先生です。
児童文学、YA作家として多くの作品を発表しておられる石崎先生が、なぜ翻訳を? と疑問に思ったファンの方もいらっしゃることでしょう。
実は、石崎先生は、海外文学好きで大の海外ドラマ好き、そしてグリシャムファンとのこと。グリシャム初の児童書を翻訳していただくには、石崎先生をおいて他はないということで、編集部が猛アタックをした結果、今回「翻訳」をお引き受けいただくことになりました。
『さよならをいえるまで』(マーガレット・ワイルドぶん、岩崎書店)など、絵本の翻訳は何作品も経験ある石崎先生ですが、長編の翻訳は今回が初めてとのこと。それだけに、多くの時間を割いて、丁寧に翻訳にあたっていただきました。
世界的ベストセラー作家・グリシャム氏の初の児童書を、日本を代表する人気児童文学作家・石崎洋司先生が翻訳するという奇跡のコラボレーションを記念し、岩崎書店編集部では石崎先生にスペシャルインタビューを実施。児童文学作家としての視点で、この作品をどう思ったか、キャラクターの描き方はどうだったかなどについて、石崎先生の思いを語っていただきました。
海外文学もお好きなグリシャムファンの石崎先生にとって、彼の初めての児童書『少年弁護士セオの事件簿』はいかがでしたか?
原書を一読したときに、上手いなと思いました。児童書として配慮して書いているところが前面に出ていて、グリシャムの「子ども向けの作品を書くぞ」という意気込みが、ものすごく伝わってきました。
グリシャムは、『法律事務所』とか『判決のとき』とか、重厚な法廷ミステリーの著者として既に人気を得ていますから、特別、子ども向けの本を書く必要はないわけです。しかし、彼はあえて書いた。そこに、法廷ものの作家として、子どもたちに法律への興味を持ってほしいという強い気持ちがあることを感じました。法律問題を自分たちの身に降りかかってくるものとして捉え、また、法を通して社会に参加してほしい。彼は、そういうことを作品を通じて伝えようとしているんだろうなと、感じたのです。
ただ、法律の知識のある彼が、教科書的に書いたのでは、多分子どもたちには読みづらいものになるでしょう。だから、グリシャムはそれを物語仕立てにしているわけですが、同時に、児童書を書くときに必要な技巧と意欲が感じられるんです。
児童書を書くには、独特のテクニックが必要です。一番大事なのは、当たり前ですが、「わかりやすく書く」ということです。ただ、これが、実は一番大変で、多くの一般文芸書の作家がいろんな面白いネタを使って書いても、なかなか成功しないのは、この「わかりやすく書く」という技術がないからなんですね。
わかりやすく書くということは何かというと、スピード感です。説明をするためには、物語の流れを止めなければなりません。でも、物語の流れが止まったら、子ども読者にはつまらないわけです。大人はある程度「ここは説明だな」って我慢してくれますが、子どもは我慢しません。物語も進めなければならない、説明も入れなければならない、しかも難しい言葉は使えない。この相矛盾するところをどう乗り切るかが児童書では命なんですけど、それがものすごく難しい。
特に、今回の作品は、司法システムの説明をきちんとしなければならない。ふつうの物語のように、キャラクターを立てる描写や、情景描写、状況設定の説明だけではすまない。とにかく説明ポイントがものすごく多いんです。
でも、難しい言葉は使えない。大人向けなら、漢字二文字の熟語で済むところを、十文字くらいの大和言葉に置き換えて書くわけですが、その分、どうしても長くなる。そこでこんどは、もたつきを感じさせないようにする工夫が必要になる。
これだけのポイントを同時にクリアするのが児童書なわけですが、そういう書き手側の目線でこの作品を眺めてみると、グリシャムは、やっぱり上手い。セオが同級生に説明するという形をとって、物語を進めながら、法律用語や司法のしくみをやさしく解説する工夫など、とても大人物ばかりを書いていた作家とは思えません。
この技巧を可能にしたのは、おそらく、子どもたちに社会に目をむけてほしいという、グリシャムの意欲です。この作品には、アメリカの社会問題がきちんと書かれています。移民問題とか、離婚問題とか、富裕層とそうでない人たちの問題とか、動物の問題とか、かなり身近な社会問題です。ストラテンバーグという架空の町の物語ではありますが、全米のいろんな町にすんでいる子どもたちは、自分の町にもこういう部分があるなと、共感できるでしょう。そのおかげで、この作品は、物語として読んで楽しめると同時に、社会勉強の教科書にもなっています。みんなで読んで話し合いもできる教材にもなる、という要素もうまく盛り込んでいて、成功しています。それらをひっくるめて、上手いな、と思います。
僕は、海外ドラマが大好きで、法廷が舞台のドラマもたくさん観ています。弁護士のおしゃれなラブ・コメディ「アリー・マイ・ラブ」をはじめ、社会派では「プラクティス」、エンターテインメント系では「ボストン・リーガル」、ラスベガスの弁護士たちの活躍を描いた「ディフェンダーズ」などなど。もちろん、往年の名作「ペリー・メイスン」も子どものころ見ました。おそらくアメリカ人の多くも、そうでしょう。 しかし同時に、一般人にとっての法廷の印象が、そうしたドラマのイメージで固まっていることをグリシャムは危惧しています。だから、「現実の法廷はテレビドラマとは違う」ということを物語の中で繰り返し伝えています。特に冒頭のところによく出てくるのですが、テレビドラマみたいに予定になかった証人が出てきて裁判がひっくり返るというようなことはありえない、というようなことをセオを通じてきちんと伝えています。そういうところも、児童書として書くにあたっての教育的配慮がかなりあると思います。
弁護士に憧れる少年が主人公。フォア文庫「マジカル少女レイナ」シリーズや青い鳥文庫「黒魔女さんが通る!!」シリーズなど、キャラを立てた人気作品を生み出している石崎先生ですが、グリシャムのセオの描き方はどのように感じましたか?
難しいところに挑戦してるなということに気づきました。
セオは、いわゆる中流家庭の育ちで、スポーツ万能ではないが、勉強はよくできる、という少年です。これは、結構読者からの共感を得にくい設定なんですよね。嫌味なくらいソツのない完璧な少年に見えますから。その不利な設定を、グリシャムが一生懸命クリアしようとしているところに、書き手として共感しました。
僕も個人的に、こういう勉強が得意な子どもを書きたいという思いがあるんです。どうしてかというと、それが難しいからです。不幸な家庭に生まれたとか、いわれのないいじめに遭っているとか、勉強ができないとか、そういうキャラであると、物語を作る時に楽なんですね。反抗する相手というのが、明確になりますから。「だれも自分のことをわかってくれない」とか、「俺たちはどうせ、つまはじきものさ」というふうに、読者の共感を呼び起こすような書き方ができるわけです。
しかし、勉強ができる子たちも、それぞれに問題を抱えているし、困っていることもあるし、不満もあるはずなんです。ただ、表面的には満たされているように見えるので、それをどう描くかというところが、難しい。現実という壁にぶつかったときの葛藤を経験させて、その子の内面的な成長を描く、というのが児童書には多いのですが、セオのように、一見、あまり葛藤のなさそうな少年だと、その部分がなかなか出しにくいという難しさがあります。それを苦労してグリシャムが書いているのが、僕にはわかりました。 実は、詳しく読むと、セオはちょこちょこときまりをやぶっているんですね。裁判の続きを見に行きたいけど、学校を抜け出すわけにいかないからと、図書館にしのびこんでパソコンを裁判所の速記システムにつないで侵入したりしています。
また、セオはスポーツマンじゃないから女の子にもてないのですが、両親の離婚裁判で困っている女友達のエイプリルのことを気遣ったり、学校で人気者の女の子のワンちゃんを動物法廷から取り戻す手助けをすることで、張り合いを感じたりしています。
ただの勉強のできるイイ子ちゃんじゃないんだよ、という場面をちょこちょこ入れることで、読者に近い存在にしようとしている。そうして、グリシャムがセオのキャラクターを「作っているな」と感じました。
ただ、キャラクターの立て方、つまり描写の方法がアメリカと日本では違っていて、初訳ではそういうところが出にくいという問題がありました。それで、改稿ではセオの一生懸命なところが前面にでるように、工夫して訳しました。
アメリカの書評では、「ジュニア向け法廷ミステリー」という新しい分野を切り開いたと評価されていますが、そのようなイメージはお持ちでしょうか?
主人公が子どもで、なおかつ子ども向けに書かれた法廷ミステリーというのは、たしかに新しいと思います。
少年探偵ものは、アメリカにも日本にもありますが、セオは、少年弁護士ですからね。書き手に十分な法律知識が必要になります。そういう意味では、グリシャムでないと書けなかったというのは、間違いないと思います。
グリシャムが、今回こういう子ども向けの法廷劇を書いた背景には、アメリカのような訴訟社会でも、法廷という場所が、ただのエンターテインメントになりつつあることに対しての危機感があったのではないかと思います。社会の中で重要な要素である司法とか法廷というものに、もっと目を向けさせたい、グリシャムはそう感じて、本書を書いたのではないでしょうか。
だからこそ、従来のベストセラー作品で見られたような、派手な事件やどんでん返しの結末ではなく、今回の作品にはあえて身近な社会的問題を、丁寧に、真面目に書き込んでいます。法律や裁判のしくみを物語の中で学ぶことができるという点で、本書は子どもの目を見開かせることができると思います。
日本の読者へのメッセージをお願いします
日本では、まず学校の先生に読んでもらいたいと思います。みなさん、日本よりも開かれたアメリカの司法システムに驚かれるのではないでしょうか。アメリカでは当たり前のこと、すなわち裁判官や検事が、選挙で選ばれることなどは、日本ではありえないことですから。
本書では、ギャントリー判事が子どもたちのために傍聴席を用意したり、担任のマウント先生に「司法に関心をもたせてくれてありがとう」と言ったりしています。ああいう場面は、日本ではまず見られませんよね。日本では、裁判官や検事がどこでどんな風に生きているかなんて、知らないでしょう? 向こうから市民に接触してくることもない。完全に別世界の人になってしまっています。
でも、アメリカではシステムとしてこうなっているということを、日本の先生たちに本書を通じて知ってもらって、司法はもっと開かれるべきものなんだというのを、大きなメッセージとして、教え子たちに伝えてほしいと思います。
なぜなら、先生方の教え子が、近い将来、裁判員になるかもしれないからです。そのときに、めんどくさいよ、とか、人を裁くなんてこわい、とか、仕事や用事で忙しいから辞退しますではいけないんだよ、ということを、先生方には教える義務があると僕は思います。 そんなとき、本書を通じて、導入されて3年目になった裁判員制度を一緒に考える機会を教室でもってもらえればと思います。本書は、法律になじみのない子どもにとって、司法への親しみをもってもらうのに格好の教材となるはずですから。物語仕立てになっているから、楽しみながら読めるし、一人でもみんなでも読めますよと、おすすめしてもらえると嬉しいです。
そして、もちろん、子どもに読んでいただきたい!
子どもの頃から司法や裁判のしくみがどうなっているか知っておくことは、とても大事なことです。なぜなら、「司法」は、小学校でも教える「三権分立」という国の根幹をなす大きな柱の一つであり、さらには法律を知ることで、世の中のしくみを知り、社会とつながることができるからです。
『少年弁護士セオの事件簿』は、それらのことを楽しみながら学べる最適のガイドになるでしょう。ハラハラドキドキのサスペンス仕立ての物語にのせて、アメリカの身近な社会問題が描かれ、その法的な解決方法が綴られているのですから。
本書では、セオが少年ながら、将来は弁護士か裁判官になりたいと夢見ていますね。彼の活躍を読んで、法律家の世界に興味を持つ子どもがひとりでも出てきてくれたらうれしいです。
僕の書いた「マジカル少女レイナ」シリーズでは、職業をテーマに書いた作品が多いのですが、それは、子どもの頃から職業意識を持って欲しい、大人たちの仕事に興味を持って欲しいという意図を強く持っているからです。子どもは成長して必ず社会に出ます。そのときに、社会の一員として、強く生きてく「力」を持って欲しいんです。
この作品で描かれている弁護士像は、今までグリシャムが書いてきたもののなかでも、かなり現実に即した姿になっています。たとえば、セオの両親はともに弁護士だけど、さほど裕福ではありません。なのに、なぜ激務である弁護士の仕事を続けているのでしょうか。それは、みんなのために、社会正義のためにこの職業はあると信じているからです。儲かるから、とか、社会的地位の高い、つまりエリート意識が持てる職業だから、などという理由で弁護士になるなんて、まちがっているし、実態に即していないよと、グリシャムは伝えようとしているんです。
本書を読んで、弁護士や司法に関わる仕事に対する理解が深まるといいし、なにより、大人たちが一生懸命に働く姿を子どもたちが感じ、自分もそんな大人になりたいなと思ってくれたらいいなと、訳者として願っています。